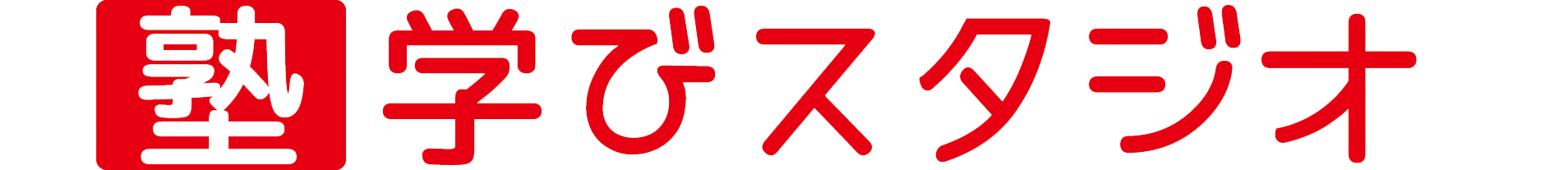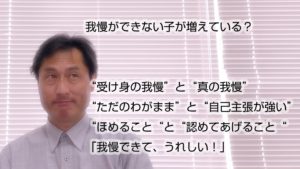計算練習や公式の暗記の中にある “落とし穴”
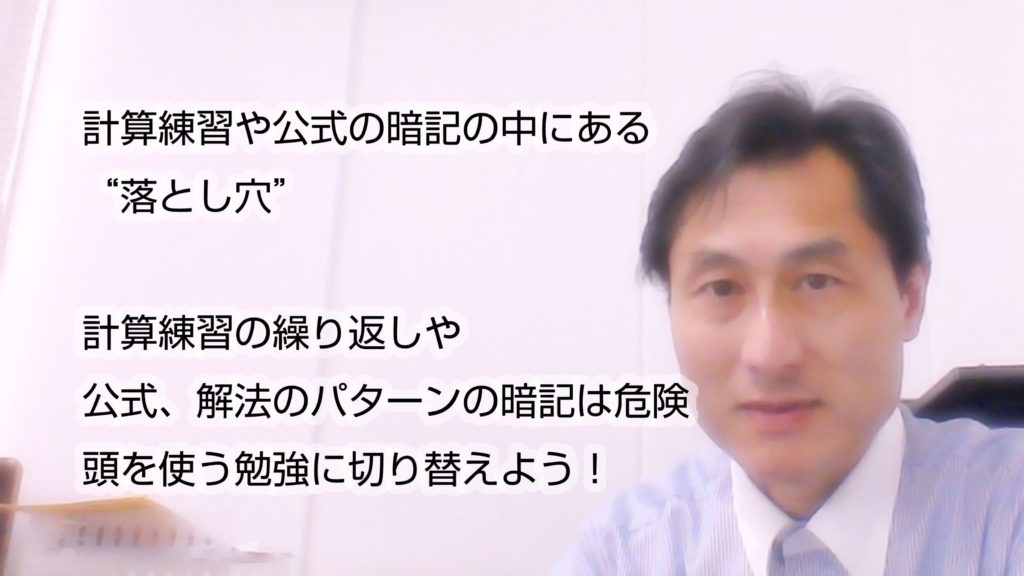
こんにちは、名張の個別指導塾 学びスタジオの奧川悦弘です。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今回は算数と公式について書きます。
∴算数=計算ではない
計算ができれば算数に有利、
そんな考え方があります。
しかし、
それは、有利であって、
“計算だけができればよい”ということではありません。
∴計算を繰り返す=頭を使うではない
計算練習をいくら繰り返しても、
頭を使うことにはなりません。
私の塾ではそろばん教室を行っています。
まさに、計算の練習です。
そろばん教室では、
イメージ脳(右脳)を鍛え、
指の巧緻性を磨き、
目標として、暗算2級以上を目指しています。
暗算2級のレベルになれば、
計算をかなり早く正確にできるようになるので、
入試の算数や数学、理科で、問題を考える時間をしっかりと確保できるようになります。
そろばんに代表される計算練習は、
あくまでも、右脳を使う練習で、
頭を使うこと、考えること、
つまり、左脳を使う練習には決してならないということです。
∴計算の落とし穴
一生懸命に計算練習していれば、
それだけで勉強した気分になってしまいます。
実際に計算力は高まり、
テストを受けても計算問題なら解けるようになります。
計算練習には目に見えて成果がついてきます。
計算練習を“頭を使う”本来の勉強と勘違いしてしまします。
また、
計算練習だけで算数の勉強を進めると、
計算を早く行うためには、
できる限り反射的・機械的にやることが望ましいので、
頭の使い方も考えることを避けるようになっていくということです。
だから、
計算問題ならいくらでも解けるけれども、
ちょっと込み入った文章問題になるとお手上げで、
考えることができなくなってしまします。
なまじ計算能力があるために、
計算だけで解けない問題を考えようとはしなくなる可能性だってあります。
∴進学率をウリにしている大きな進学塾の指導、本当に子どものため?
大きな進学塾で難関中学校への進学を目指すクラスでは、
例えば灘中学校の第一日目の算数の入学試験問題を30分で解かせようとします。
実際の入試では試験時間は60分、問題数は12問あります。
これを30分で解くためには、単純計算で1問にかけられる時間は2分ちょっとです。
例えば次のような難問です。
「3つの容器A,B,Cにあわせて600mLの水が入っています。容器Bの水の体積は容器Aの水の体積の1.5倍です。容器Aから容器Bに水を40mL移すと、容器Bの水の体積は容器Cの水の体積の1.4倍になりました。水を移したあとの容器Bの水の体積は□□mLです。」
一読しただけでは、問題の意味を理解することさえ難しいのではないでしょうか。
こんな問題を2分ちょっとで解くためには、どうすればよいか。
いちいち考えなくても解けるようひたすら訓練するのです。
なぜ、あえて時間を短く切って競わせるのか。
それは、
実は、そんな塾に入塾する子どもたちの中には、
もともと柔らかな頭に恵まれた『1%枠』に入る子どもたちがいます。
進学塾としては、
その『1%枠』の子どものための授業を行い、
彼ら彼女らが合格することによって、
難関中学に合格者をたくさん出すことが、大切だと考えているからです。
∴公式、解法のパターン、解法テクニックをひたすら暗記
進学率をウリにする進学塾では、
暗記力に秀でた子どもたちを徹底的に鍛えるのです。
彼らに対しては、まず公式や解法のパターン、解法テクニックを、これでもかというぐらいたくさん覚え込ませます。
(大手進学塾が独自に作っている教材ともなれば、驚くべき数のテクニックが掲載されています。可能な限り短時間で、正解を導き出せるように、ありとあらゆる過去問を分析し、パターン化しているのです。)
子どもたちには、詰め込み教育をみっちり行います。
この問題にはこの解き方、別の問題にはまた別のテクニックといった案配で、
問題のパターンに応じた解法を覚え込ませるのです。
子どもたちに求められるのは、
問題を見極める能力と、
それに最適な解法を記憶の中からマッチングさせて引き出す能力です。
自分の頭を使って考えていては時間の無駄だといわんばかりに、
授業で解き方を叩き込まれます。
∴確かに成績は上がりますが、見せかけの成績は、危険
しかし、そんな訓練をいくら繰り返しても、
頭が使われない限り、頭が柔らかくなることはありません。
頭を使って考える訓練をしない限り、
頭を使えるようにはならないのです。
これこそが、
子どもを考えなくする最高に危険な方法といえるのではないかと思います。
いくらがんばって問題の解き方を数多く覚えたとしても、
解き方を教わっていない問題が出た時には、
手も足も出ないのです。
本来ならがんばり屋さんなのですから、
考える訓練をさせてあげれば、必ず考えられるようになったはずです。
そんな子どもたちを考えない子どもにしてしまう。
これは恐ろしいことです。
∴仮に、憧れの中学に、暗記力によって突破しても
名門私立中学校に入れば安心というわけではありません。
そこから新たな学校生活が始まるのです。
トップレベル校が本来求めているのは、
柔らかな頭を持った子どもです。
そうした学校の多くが中高一貫校で、
独特なカリキュラムを組んでいます。
まず、授業の進度が恐ろしく速い。
例えば数学なら、中学3年生までの内容を中学1年生の終わりまでには終えてしまい、
直ちに高校数学へと進んでいきます。
そして中学校を終える頃には、高校の数学Ⅱを修了しているのです。
中学入試の算数問題なら、
解法を必死で暗記することで何とか対応できたかもしれません。
けれども、
本質的な論理的思考力が求められる数学に、
暗記は通用しません。
自分の頭で考えて理解することができなければ、授業にはまったくついていけないのです。
∴挫折につながる可能性がある
憧れだったトップ校にせっかく入れたのにも関わらず、
途中で脱落してしまう。
小学校時代のがんばりが水の泡と消えてしまうのです。
仮に学校の授業についていけなくなった結果、
途中でやめてしまうようなことにでもなれば、
その傷は一生ついてまわる危険性もあります。
∴子どもの頭が柔らかい?
子どもがまだ習っていない問題を、挑戦させてください。
「無理だ、こんな問題は習っていない」
と音を上げるようなら、
頭が柔らかくないと判断できます。
逆に、
この問題を面白がり、
時間をかけてあれこれ試行錯誤しながら考え続けられるようなら、
頭の柔らかさは相当なものだと考えられます。
もちろん、途中で投げ出したとしても何も問題はありません。
頭を使う訓練をすれば、誰でも必ず頭は柔らかくなっていきます。
∴まとめ。マジックワード「なぜ?」「どうして?」をいつも意識する
子どもの力を、
“考える”勉強、“頭を使う”本来の勉強に振り向けてあげましょう。
がんばる力のある子どもたちが、
“考える”勉強に集中的に取り組めば、
驚くほど伸びる可能性があります。
公式の暗記によってではなく、
考える力をつけたことによって、
難関校に合格にできれば、
憧れの中学でも、
“考える”勉強をしてきたことが、
大きな力になり、
より広く、より深く、より楽しく学ぶことができると思います。
「なぜ?」「どうして?」を口くせに、
いつも意識することから始めましょう!