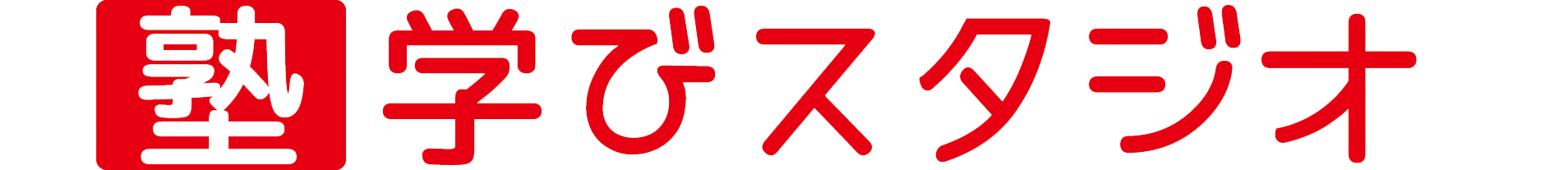読み聞かせの目的は"本って楽しい"
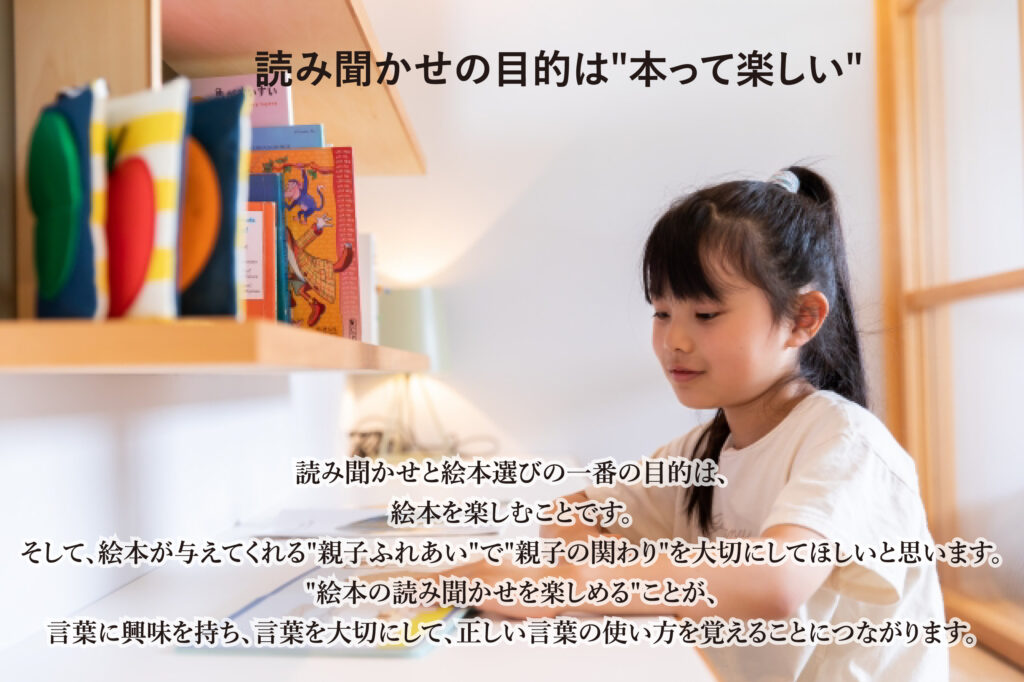
こんにちは、三重県名張市の個別指導塾 学びスタジオの奧川悦弘です。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今回は、絵本の読み聞かせについて書きます。
正しい言葉の使い方を覚えるための原点は、”絵本は楽しい”にあるのかもしれません。
∴読み聞かせる絵本を選ぶ際の注意点
「子どもたちにこんなメッセージを伝えたい」
「子どもに役立つテーマの絵本を選ばなくては」
絵本選びにいろいろなことを考えます。
しかし、重要なのは
「絵本って楽しいね」
「絵本を読んでもらうのってうれしいね」
という気持ちです。
読み手と聞き手が、
テーマやメッセージよりも、
まずは楽しさを"共感する"ことが大切です。
∴具体的にはどのような絵本
親(読み手)が
「好きだな」「読みたいな」と思う絵本を選ぶことが大切です。
自分のなかに好きな絵本をストックしていって、
子どもの成長にあわせて選ぶことができるといいですね。
「この絵本を読みたいな」
「読んであげたいな」
という読み手自身がウキウキするような気持ちが大事です。
∴年齢別の絵本選びのポイント
年齢別の絵本選びのポイントは次の通りです。
⓪0歳。楽しんで発音できる両唇音を
❤︎ボール紙でできている・角が丸くなっている
0歳児に向けでは、
ボードブックといって、
分厚いボール紙で作られている絵本がとくにおすすめです。
赤ちゃんに配慮したつくりになっていて、
角が丸く加工されています。
❤︎擬音語・擬態語(オノマトペ)がたくさん用いられている
言葉が未発達なので、
赤ちゃんが楽しめ、
そして言いたくなるような音を使っているかどうかも、
0歳の赤ちゃんに絵本を選ぶ際には大切なポイントです。
❤︎両唇音がたくさん用いられている
「まみむめも」
「ばびぶべぼ」
「ぱぴぷぺぽ」といった、
上下の唇をあわせて発音する音を「両唇音(りょうしんおん)」といいます。
この両唇音は、
赤ちゃんが初期に獲得できる音で、
楽しく発音でき、
思わず言いたくなってしまう音です。
ですからそういった音がたくさん出てくる絵本であれば、
赤ちゃんも一緒に楽しむことができるでしょう。
❤︎身近なものを扱っている
赤ちゃんの世界は、
大人と比べてとても狭いです。
外出するのも近くの公園まで、
家で目にするものも、
天井や家族の顔ばかり……。
だからこそ、
赤ちゃんにとって身近なテーマを扱った作品を選ぶということも、
ひとつのポイントでね。
❶1歳。子どもたちのブームにあわせて
1歳の頃には、
子ども自身でできることが、どんどん増えていきます。
その"発達"にあわせて、
あるいは子どもたちのなかで、いま"ブーム"になっていることをもとに、
絵本選びます。
たとえば、
"ジャンプができるようになって、楽しくてたまらない"
そんな子どもたちには、
ページをめくるたびに、
さまざまな動物たちが飛び跳ねる絵本とか
子どもたちをよく観察していると、
今どんなことに興味があるのか、
どんなことが流行っているのかがわかりますから、
それを絵本選びに活用してみます。
❷0歳から2歳。絵本選びは親子のかかわりが大切!
2歳になると、
ちょっとしたストーリー性のある絵本も楽しめるようになってきますが、
0歳から2歳までの絵本選びでは、
共通して"親子のかかわり"が重要なポイントだと考えています。
❤︎『ぶう ぶう ぶう』(講談社)
この絵本は、おーなり 由子さんと、
はた こうしろうさんのご夫婦が、子育てが大変ななかで、
子どもの体に「ぶう」とするだけで笑顔の時間ができたご経験から生まれたそうです。
今は子育てが"しんどい"時代だと思いますが、そんななかで絵本は
「これだけでいいんだよ」
「こんなことをするだけで一緒に楽しめるんだよ」と、
子どもとのかかわりを提案してくれます。
❸3歳。絵本に向かう力がでてくる
3歳になると、
"絵本に向かう力"が出てきます。
そんななかで絵本を選ぶときには、
子どもたちが理解しやすいように、
できるだけシンプルな絵本を選ぶとよいでしょう。
"繰り返しのパターン"を用いた絵本はおすすめです。
シンプルな言葉や展開が繰り返される絵本は、
ページをめくるたびに楽しみがあるので、
子どもが「次はどうなるんだろう?」という気持ちを、
最後まで持ち続けることができます。
❹4歳。絵本に夢中になるパワーが付いてくる
4歳になると、
子どもは絵本にぐっと引き込まれるようになります。
4歳の読み聞かせでは、
絵に見入ったり、ストーリーの展開にワクワクしたり……
より"じっくり味わえる"内容の絵本を取り入れます。
❺5歳。長くなければダメということはない、楽しさを
5歳児は理解のスピードも早いので、
昔話のようなボリュームのある絵本も楽しめるようになります。
長いストーリーを、
何日かにわたって読んであげるのもいいですね。
∴長いお話、集中力より、楽しさを
ただ、
年長さんになったから、
長いお話でなくてはならない
小学校にあがるから、
長いお話に慣れさせなくてはいけない
ということはありません。
集中力をしっかり身につけて欲しいなどと考えがちなのですが、
まずは「絵本の楽しさ」というところを大切に考えるようにしましょう。
また、
だじゃれやさかさま言葉、
早口言葉といった言葉のおもしろみを楽しむことができます。
絵本を通じて、
そのような言葉遊びを楽しむのもおすすめです。
『だじゃれどうぶつえん』(絵本館)
『はやくちこぶた』(瑞雲舎)…
∴教えるのではなく、わかるようになったから"楽しもう"と考える
「ひらがなを教えよう」
「言葉を教えよう」と強くて考えてずに、
「言葉の楽しさがわかるようになってきたから、この絵本を読んで一緒に楽しもう」
という提案をしてみてください。
そして、
絵本を通じて「言葉って楽しいね」ということを、子どもに伝えるのが一番です。
∴読み聞かせの前の環境づくり
よく絵本を読むまえに
表紙の次のページの"見返し"を見せることで、
少しの間が生まれます。
そこで子どもたちは
「さあ、はじまるぞ」と気持ちを落ち着けることができます。
∴"見返し"にも意味が
絵本によって、
絵が描かれていたり、
単色だったりと
さまざまな"見返し"
実は物語に関連した色が使われているなど、
大切な意味が込められています。
だから"見返し"は、
絵本が読み聞かせをする前の
「今日はどんなお話かな、楽しみ」
という環境作りになります。
∴まとめ
読み聞かせと絵本選びの一番の目的は、
絵本を楽しむことです。
そして、
絵本が与えてくれる"親子ふれあい"で
"親子の関わり"を大切にしてほしいと思います。
"絵本の読み聞かせを楽しめる"ことが、
言葉に興味を持ち、
言葉を大切にして、
正しい言葉の使い方を覚えることにつながります。