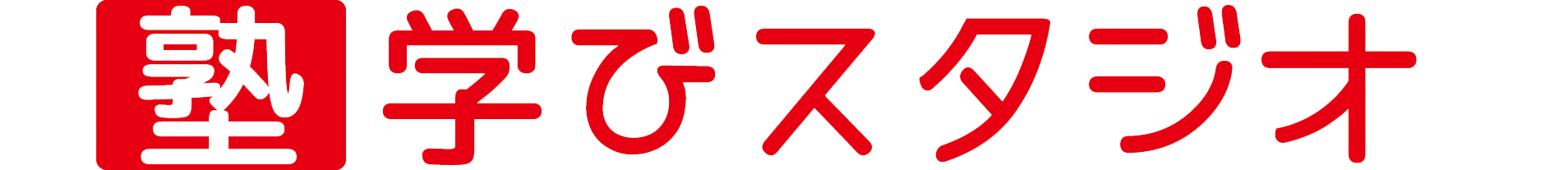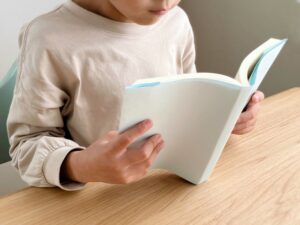「学び」と「わかる」、「真似び」と「分ける」

こんにちは、学びスタジオの奧川悦弘です。
ご訪問いただきありがとうございます。
今回は、「学び」と「わかる」について書きます。
∴子どもの学び
子どもは真似をすることが大好きです。
そして、
子どもには柔軟性が備わっているため、
真似をすることが得意です。
大人の言葉を自然に真似て、言葉を増やし、
大人の動作を自然に真似で、行動力を身について、
友だちのカッコいいところを見つけて、それを自然に真似ます。
そんなふうにして子どもたちは学習をしていきます。
∴「学ぶ」ということ
「学ぶ」という語の語源は、「まねぶ」です。
つまり、「まねる・真似をする」です。
「真似をする」ことは、重要な学習方法です。
∴「分かる」ということ
「分かる」という語の語源は、「分ける」です。
だから、
「わからない」状態は、分けられていない、混沌とした状態のことです。
「きっとこれはこうなるだろう」と
見分けることができ、
あらかじめ予想できる物事については不安を感じませんが、
予想できない物事については「これからどうなるのだろう」と不安を感じます。
それが、
わからないことです。
∴真似をするから、分けることができる。
一つのことを
真似をし続けていると、
そのことの本質が理解でき、
他のことと区別できるようになってきます。
これが、
物事をくっきりと分けること、
つまり、わかることです。
∴分けることが創造につながる
そして、
いろいろなことを分けることができると、
そこから、
新しい発想が生まれることがあります。
それが、創造ですね。
∴真似で独創性が育たないことはない
真似では独創性が育たない?
しかし、
優秀な芸術家や科学者、スポーツ選手は、
先人を徹底的に真似ながらそれを吸収し、
そこから独創性を生み出しています。
このように、
「個性が大事」ということは、
真似はいけないと考えるのではなく、
習字が手本を見て書写をするように、
まさに「まねぶ」ことによって、
独創性が出てくると考えるべきです。
∴「まねぶ」時の注意点
「まねぶ」時は次の点に注意し、あわてさせないことです。
❶そっくりに真似する。
❷難しそうであれば、少しずつに分ける。
❸少しずつ分けて、何度も同じところを繰り返す。
❹少しずつやさしいことから、難しいことへと進んでいく。
∴「そっくり」から「オリジナリティ」
例えば、
子どもにハーモニカで「同じ音を出してごらん」と言うと、
ハーモニカの演奏を一生懸命聞いて、
どうすると同じになるのかを強弱や長さ・音色を調整しながら思考錯誤をします。
そうして同じになったときに、
今度はどうすればよりいい音が出るのかを考えることができるようになります。
このように、
集中してそっくりに真似をしようとすると、
観察力が育ちます。
最初は真似であっても、
そのうち子どもたちはオリジナリティを生み出し始めます。
∴まとめ。
「学ぶ」は「真似る」
「わかる」は「分ける」
真似をすることは大切な学習方法です。
そっくり真似ることで、
観察力が育ち
見分けることができます。
そして、
「こうしたらもっとよくなる」と
オリジナリティーが生まれます。