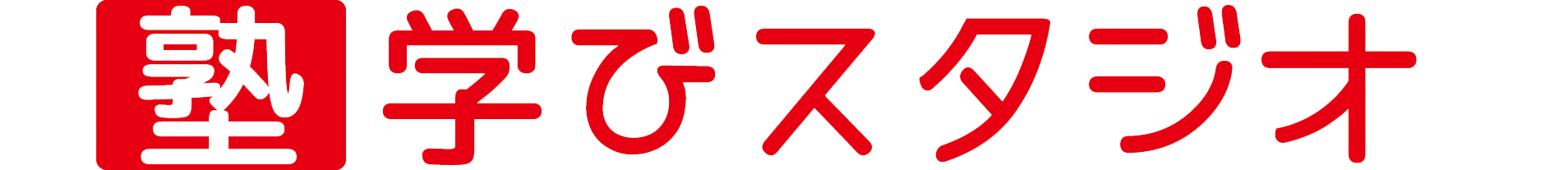賢い子どもは、日常生活でも学んでいる
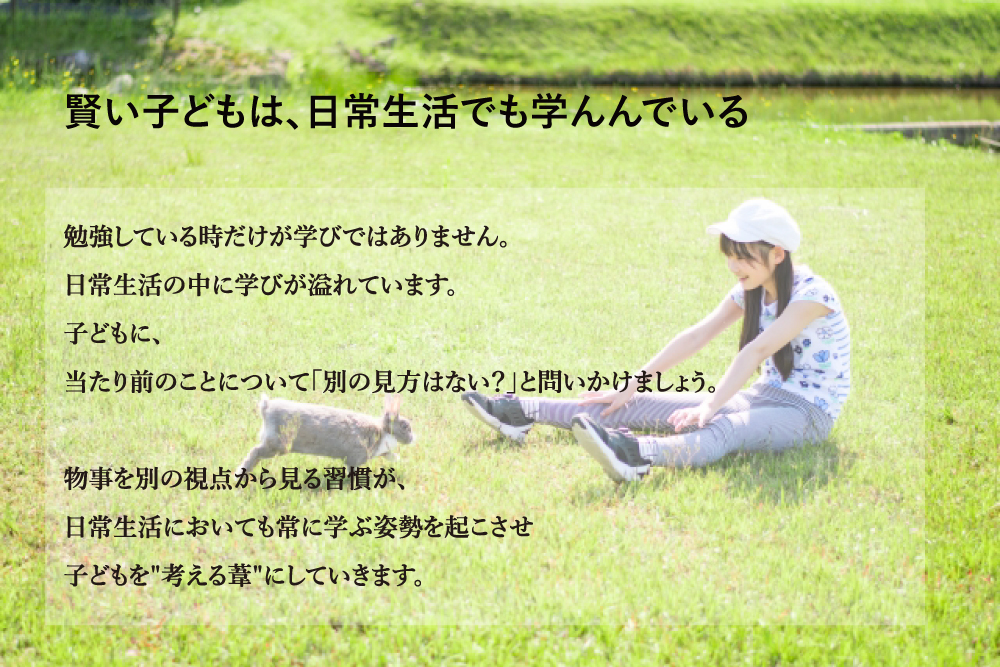
こんにちは、学びスタジオの奧川えつひろです。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今回は、賢い子どものについて書きます。
▲賢い子どもは、始終“学んで”いる
賢い子どもは、いつでも学び続けています。
勉強時間の長さだけで
差がついているのではありません。
▲"学び”のタイプは3つ
学びには、3つのタイプがあります。
❶勉強中でも学んでいないタイプ
授業中に説明を受けたこと、
テキストに書いてあることを
書き写す“作業”を黙々と行うタイプです。
これは、
書記をしているだけで、
学んでいることにはなりません。
でも、
写すことで勉強した気になっている。
案外多いのではないでしょうか。
❷ 勉強中だけ学ぶタイプ
授業中はしっかりと学び、
さらに家で予習・復習など、
勉強する時間の中は
しっかりと学ぶタイプです。
❸寝ているとき以外、すべて学ぶタイプ
人と話をするときも、
テレビを見ているときも、
街を歩いているときも、
何かを感じ、考えるタイプです。
自分の意見を持つ習慣がついています。
それによって教養が深まり、
考える力が深まり、
表現力もついていきます。
▲賢い子どもになるには
賢い子どもになるためには、
"気づく楽しさ、
知る楽しさ、
考える楽しさ"
を体験させてあげることが大切です。
▲他と違う意見を考えさせ、言葉にする
超できる子どもにするための方法として、
「別の見方ない?」
「別の意見ない?」……
と別の角度から見れるように導いてあげましょう。
このような導きによって、
自然と“気づき➡︎知り➡︎考える”ようになっていきます。
そして、
子どもが発言したら、
その内容に対して絶対に否定はしません。
じっくりと聞いてあげましょう。
これを習慣化すると、
頭の構造が変わってきます。
▲既存の考えに流されない
既存の考えに流されず、
日頃から“人とは違った考え”を子どもに持たせるように会話をし続けると、
学力に大きなインパクトを与えるようになっていきます。
▲考える葦
パスカルが
"人間は考える葦”
(人間というのは弱い面もたくさん持って いるが、"考える"という働きがあるからすごい)
と言っているように、
日常の一瞬一瞬を大切にして、
いろいろなと"考える"ことができたら
"すごく楽しい"と思います。
▲まとめ。賢い子どもは、日常生活でも学んんでいる
勉強している時だけが学びではありません。
日常生活の中に学びが溢れています。
子どもに、
当たり前のことについて
「別の見方はない?」と問いかけましょう。
物事を別の視点から見る習慣が、
日常生活においても常に学ぶ姿勢を起こさせ
子どもを"考える葦"にしていきます。