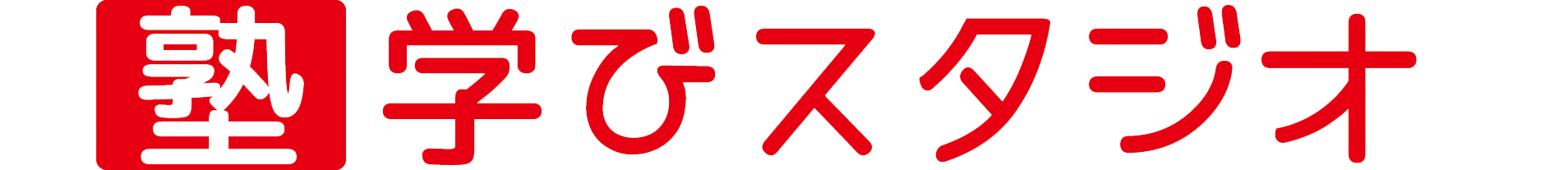つながることは好奇心

こんにちは、名張の個別指導塾 学びスタジオの奧川悦弘です。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
私は、奥川悦弘と申します。
名前は“えつひろ”と読みます。
その意味は、“悦びを弘げる”です。
この名前をつけてくれた両親に感謝し、
この名前を実現できるように生きていきたいと思っています。
今回は、好奇心について書きます。
∴好奇心とつながることは、本能
人は一人では生きられません。
生まれた時、
笑でで、
可愛い泣き声で、
親とつながろうとします。
親もその可愛さに応えようとします。
目を閉じて下さい。
何か聞こえませんか。
そうです。
いろいろな音です。
耳から、
いろいろな音が聞こえます。
その中から、言葉を覚え、
そして、
話すようになります。
言葉で親とつながろうとします。
親も未熟な子どもの言葉を聞いて、
理解しようとして、
それに応えようとします。
目が見えてきます。
親を目で追うようになります。
いつもいてくれる親がわかるようになります。
最初は、目に見える親の存在を認識します。
親も子どもに目を合わせて応えます。
このような、
子どもがつながりを求め、
親がそれに応えてくれるという関係から、
目に見えなくても、
親が存在して、
つながっていることが理解できるようになります。
「目に見えなくても、親がいて、つながっている」
という安全基地を育んでいきます。
安全基地を持っていると、
外に向けて、
さらにつながろうとできます。
どんどんつながりを求めようとします。
このつながるために、
笑ったり泣いたり、
耳から言葉を覚えたり、
目で観察したり、
それを、口や体で表現しようとすることは、
人間が生まれ持った本能であり、
それが、好奇心です。
だから、
子どもは好奇心旺盛なのは、
本能です。
また、
人とのつながりを求めるのも、
本能なのです。
∴好奇心とつながることと、それに応える環境
さらに、
子どものするアウトプットに応えてくれる環境が必要です。
つまり、
じっくりと話を聞いてくれて、
認めてくれる人がいる、
困っていると、
一緒に考えてくれる人がいるという環境です。
子どもの頃は、
それは親の安全基地です。
好奇心
一緒
安全な場所
の三位一体が、
子どもの教育には大切だと思います。
∴大切がキーワード
家族
愛情
好奇心
そして、学び
です。
∴何のために勉強するか
よく「自分のためだから、勉強しなさい」と言います。
自分のためなら、
知識を利用して自分のために使うことになります。
それは、
自分を守るために、
間違った方向に使われる可能性を含んでいます。
例えば、
自分の間違った行為を認めたくないために、
知識を使って、正当化するかもしれません。
嘘を正当化するために。
一方、
家庭で、愛情を受けて育って、
安全基地を持っている子どもは、
「勉強は、自分のためでもあり、みんなのためにもするんだよ」と話すと、
容易に理解ができ、同感できると思います。
みんなのために勉強していると、
勉強で得た知識はみんなのために使おうと思え、
また、みんなの知識も尊重しようと考えます。
先ほどの例でいえば、
自分の間違いを誠実に認めて、
嘘をつくために知識を使う必要がなくなります。
この、みんなのために勉強するという気持ちが、
人とつながる楽しさをより強めます。
∴知識がなければ、創造力は生まれない
今、人工知能が発展し、
知識を覚えたり、考えたりすることは、
人工知能の方が優れていると言われ、
知識を詰め込む、勉強する必要がなくなると言われています。
一方で、
日本のこれまでの教育は、
知識偏重、
偏差値偏重
と言われ、
知識の詰め込み教育がなされてきました。
それを反省し、見直され、
個性を尊重するゆとり教育、
脱ゆとり教育、
”生きる力”教育
と教育の方向が変わってきました。
”生きる力”教育の目標は、
❶実際の社会や生活で生きて働く、知識と技能を身につける
❷未知の状況にも対応できる、思考力、判断力、表現力などを身につける
❸学んだことを人生や社会に生かそうとする、学びに向かう力、人間性などを身につける
としています。
人工知能などと共存しながら生きることを求めているんだと思います。
この生きる力教育は、大きな目標だと思います。
しかし、
私は、
知識偏重は悪いことは思いません。
いろいろな知識があって、
初めて、その知識が生かされて、
思考力、判断力、表現力が磨かれ、
新しいものを創造するアイデアが生まれるからです。
∴どのように学ぶかが大切
一方的に教えることは、
考える力を弱めます。
また、
手取り足取り、噛み砕いてわかりやすく教えることも、
受け身で、考える機会を奪います。
だから、
自分でしっかりと読むことが大切になります。
読めないから、勉強ができないんです。
読めるようになると、
自然と勉強はできるようになります。
自分で読んで考えるを基本として勉強することです。
江戸時代の藩校や寺子屋で行われたように。
わからない時には、
答えを教えるのではなく、
どのようにしたら解決するかを一緒に考えることです。
そして、
勉強したことをアウトプットする機会を与えること、
アウトプットしたことに、
しっかりと応えてあげることです。
そのような勉強が、
子どもの自主性を育て、
知りたいとい知的好奇心を育てると思います。
∴国語と算数が、好奇心の土台となる
国語では、語彙力、読解力をつけると同時に、
読解文や読書に書かれてある内容を通じて、人間性が育めます。
算数では、大小、長短、遅速などと算数の言葉と意味を理解して、
計算と言葉のつながりを学び、
論理的な思考を身につけたり、
パズルや積み木などを通じて、図形のセンスを磨きます。
国語と算数は、
学力の土台になりますので、
学び方と知識をしっかりと時間をかけて身につけていきます。
国語と算数のしっかりした土台が、
いろいろなことを学ぶことを
楽にして、楽しくし、
本能である好奇心を大きく育てることにつながっていきます。
∴まとめ
子どもは、
親と、そして、周りの人や周りの物事へとつながることを求め、
どんどんその範囲を拡げていきます。
このつながろうとすることが、
好奇心です。
好奇心は自然に生まれてきます。
生まれてきた好奇心を潰さないように、
その好奇心を理解し表現できるように、
国語力と算数力を育てましょう。