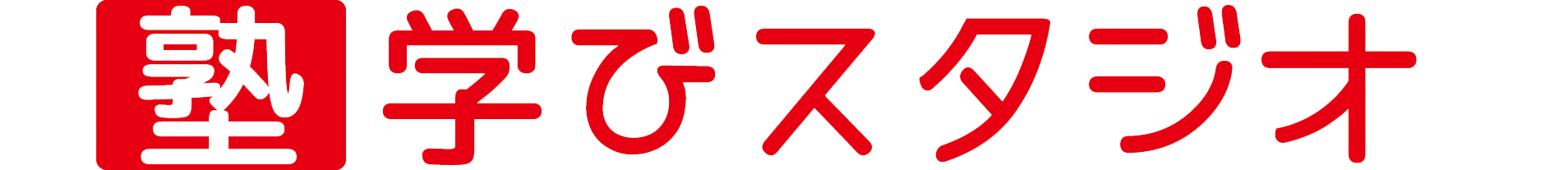書き写し読書は、納得できる生きた読書!
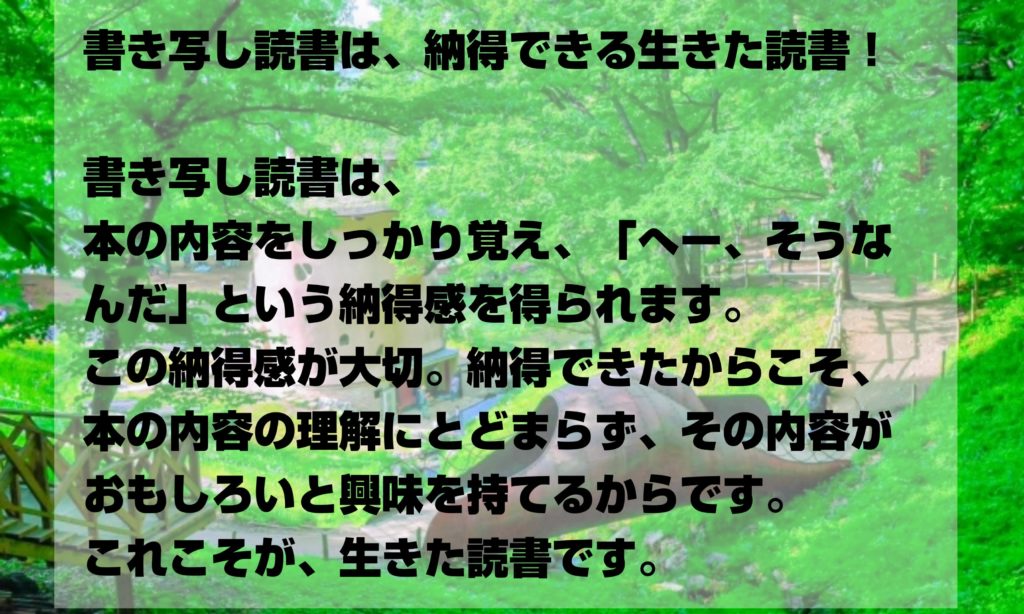
こんにちは、学びスタジオ®︎東大阪瓢箪山教室の塾長の奧川えつひろです。
情報が多く、
速さを重視した読書をしていて、
「内容をしっかり理解できないのではないか」と感じることはありませんか。
今回は、本の内容を確実に身につけることができる精読について書きます。
❤︎精読の3つの方法
❶音読する
❷本に書き込見ながら読む
❸書き写しをする
このなかでも、
"書き写し"は、最もていねいな精読です。
書き写しは、
本の内容を正しく認識するのに非常に役立ちます。
❤︎書き写し読書がいい理由
❶インプットとアウトプットの繰り返しによって記憶に残る
①本を読む(インプット)
②読んだ文章を書き取る(アウトプット)
③自分が書いたものを見る(インプット)
……
情報を入れたり出したりする作業が、
記憶を向上させます。
❷誤読を防ぐことができる
速く文章を黙読すると、
脳はおのずとわからない部分を読み飛ばしたり、
文脈を勝手に解釈したりしてしまいます。
1文字1文字丁寧に書き写せば、
文字に意識が集中するため、
誤読につながる状況を防ぐことができるようになります。
❤︎書き写しによる読書方法
本に書かれている文章をすべて書き写すのが理想です。
しかし、
実際にそれを行なうのは非常に困難です。
❤︎書き写し読書のステップ
ステップ❶気になる箇所へ線を引きながら、一度通読する
ステップ❷線を引いた箇所のうち特に重要な部分を囲い込み、ノートへ書き写す
ステップ❸各章末の結論部分を3回読んだあと、もう一度通読する
❤︎ステップ❶の"線引き"
"線引き"は、線を引いた内容を重要な情報だと脳に認識させる効果があります。
❤︎ステップ❷の"囲い込み"
"囲い込み"は、
重要な内容をいっそう強く認識するために行ないます。
目安として、
囲い込むテキストの量の全体の10分の1程度にとどめます。
また、
わからない箇所を読み返したり、
知らない単語の意味を調べます。
感銘を受けた箇所は、
「勉強になった」「納得できた」…
簡単な感想も余白へ一緒に書き込みます。
これをすると、
感情を伴う「エピソード記憶」になり、
本の内容が覚えやすくなります。
❤︎ステップ❸で仕上げ
各章末の結論部分を3回読んだうえで、
もう一度通読します。
ここまでやっていくと、
本の内容のほとんどが理解できるようになっています。
❤︎書き写し読書の効果
❶"わかったつもり"が減り、納得感が高まる。
読む速さだけを重視した読書では、
わかりにくい言葉を前後の文脈でなんとなくとらえてしまいます。
しかし、
書き写しをすると、
「この単語はどういう意味だ?」
と立ち止まることができ、
本を読み返したり、
辞書で調べたりして、
本の内容をより深く理解できるようになります。
ひとつひとつの言葉を丁寧に読み解くと理解が深まり、
「なるほど!」
という納得感が高まります。
❷読書が楽しくなっる
知らなかったことを知ることは、
楽しいことです。
理解できれば、
その内容を実生活に役立てらことができます。
「なるほど、そうなんだ」
という納得が増えると、
読書がグーンと楽しくなります。
❤︎まとめ。書き写し読書は、納得できる生きた読書!
書き写し読書で精読をするには、
ちょっと大変で時間がかかります。
しかし、
本の内容をしっかり覚えることができ、
「へー、そうなんだ」
と納得感を得られます。
この納得感が大切です。
納得できたからこそ、
内容の理解にとどまらず、
その内容がおもしろいと興味を持つことができるからです。
これこそが、
生きた読書ではないでしょうか。
子どもたちに、
音読と共に、書き写し読書を通じて、
本を読む楽しさを実感し、
内容を正確に理解するスキルを磨いていってほしいと思います。