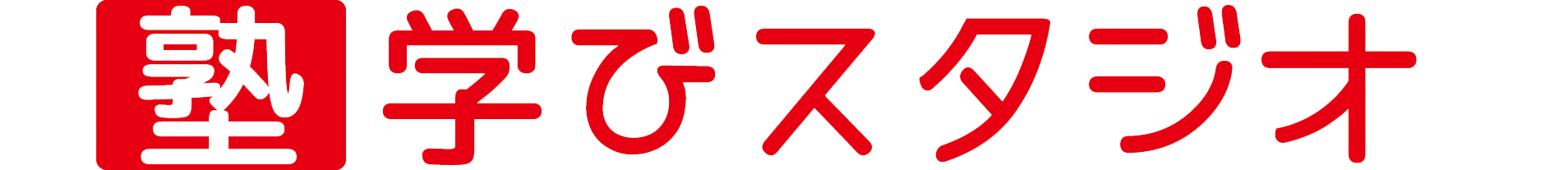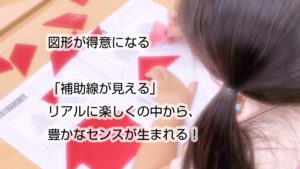学力の基本は"丁寧さ"を身につけること
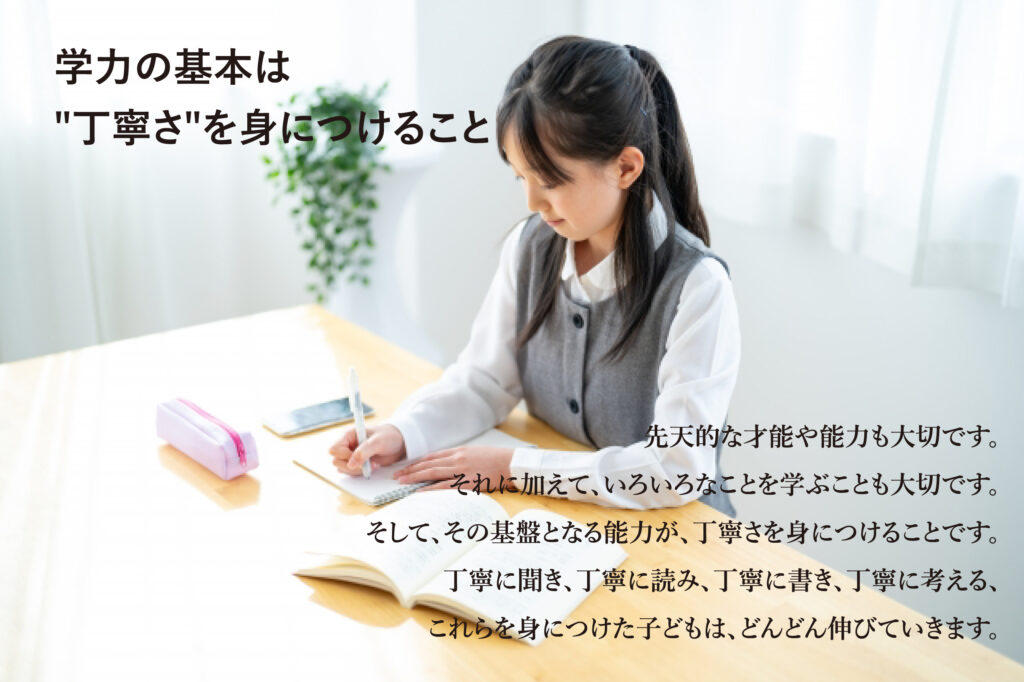
こんにちは、三重県名張市の個別指導塾 学びスタジオの奧川悦弘です。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今回は、学力の基礎について書きます。
∴ぬり絵と折り紙
ぬり絵と折り紙を例にあげましょう。
ぬり絵といっても、
ただ塗るだけではだめです。
色鉛筆を使い、
指で鉛筆を“丁寧に”動かす練習をします。
折り紙も
“丁寧に”紙の隅と隅を合わせて折ることが大切です。
一生懸命にぬりえや折り紙をする。
きめ細かな作業ができることが大事です。
ぬり絵や折り紙を通じて、
いろいろなことができるようになります。
∴えんぴつの使い方を習得
鉛筆の使い方が習得できます。
文字の"とめ、はね、はらい"がすぐに身について、
きれいに書けるようになります。
∴落ち着きや集中力に影響
それだけでなく、
きめ細やかな作業ができるかどうかは授業中の落ち着きや、
その子の集中力にも影響します。
これは文字の上達以前の、
学習に向かう姿勢にも関わってきます。
∴雑な子ども
行動すべてを雑に終わらせてしまう子どもには、
集中力がなく、文字もなかなか上達しません。
そうすると、学力もなかなか伸びません。
ボールを投げてもぎこちない、
話をさせてもぎこちないなど、
あらゆる場面にむらが出てきます。
∴丁寧さ身につけた子ども
丁寧さを身につけた子どもは、
時間をかけて根気よく続けるため、
集中力などの精神力も身につきます。
指先を使うきめ細やかな作業は、
精神面や学力、運動能力も育みます。
∴えんぴつを持てるようになったら
えんぴつを持てるようになったら、
四角い升目をつくり、
それを鉛筆で縦、横、右斜め、左斜めと塗らせていく作業を
子どもと一緒にやってください。
これだけでも、丁寧さと鉛筆の使い方の両方が十分に身につきます。
∴"子どもと一緒に、丁寧に"がポイント
子どもとの時間、距離感をうまく確保できず、
ついつい手を出しすぎてしまったり、
あそんでいるときは放任してしまったり……。
とにかく保護者は、
子どもを見てあげる時間をつくることです。
子どもが書いたり、描いたりした物を見てあげる、
宿題の答え合わせを一緒にしてあげる、
そして何より
一緒に丁寧に作業をしてあげることです。
親と一緒になにかをすることは、集団生活の基礎になってきます。
人の話を聞く、自分の思いを伝えるといった基本も身につきます。
∴今、自己主張が強すぎる子、まったく自分を出さない子の二極化している
どちらも集団行動ができず、学力にも影響がでます。
一緒に作業をしながら、
こどもの思いを引き出してあげることです。
「どうしたいの?」「どう思ったの?」と聞いてあげてください。
自己主張を強くするときは、
その主張を抑え込むのではなく「お母さんの話も聞いて」と、
ストップさせてあげることです。
そうやって、
自分の思いを伝えたり、
人の話を聞ける姿勢を培っていきます。
∴学習の基礎は、日常生活に溢れている
保護者と過ごす家での丁寧な関係性が、
"聞く・話す・読む・書く"という学習の基盤をつくっています。
そして、
それは日常生活の中のいろいろな場面で溢れています。
∴考えることも丁寧に
1つのことを10回味わうことばを紹介します。
「はてな?」
「なるほど!」
「そうか」
「でもね」
「ええと…」
「しかし」
「たとえばね」
「つまり」
「やっぱり」
「わかった!」
これらは、“話を聞く方法”を示したものです。
∴論理的に内容を理解できるようになる
小学生の間に、
この”話しを聞く方法”を身につけると、
自然に
要点はなんだろう、
自分ならどう考えるのかを
考えながら聞くことができるようになります。
そうすると、
本当に子どもの学力は伸びていきます。
この方法に基づき丁寧に聞くことができれば、
論理的に内容を理解することができるようになります。
∴まとめ。
先天的な才能や能力も大切です。
それに加えて、
いろいろなことを学ぶことも大切です。
そして、
その基盤となる能力が
丁寧さを身につけることです。
丁寧に聞き、
丁寧に読み、
丁寧に書き、
丁寧に考える、
これらを身につけた子どもは、
どんどん伸びていきます。