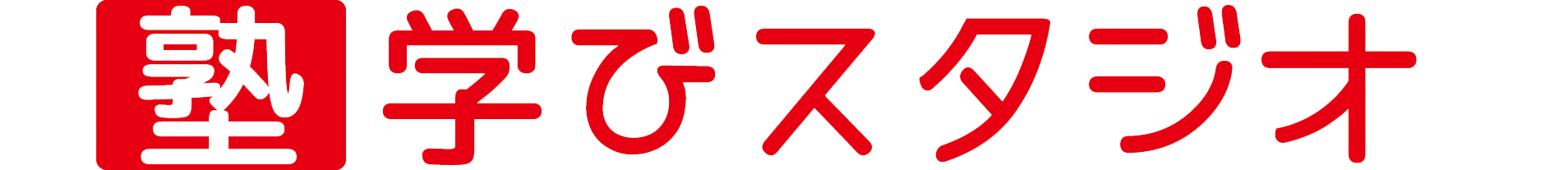図形が得意になる「補助線が見える」
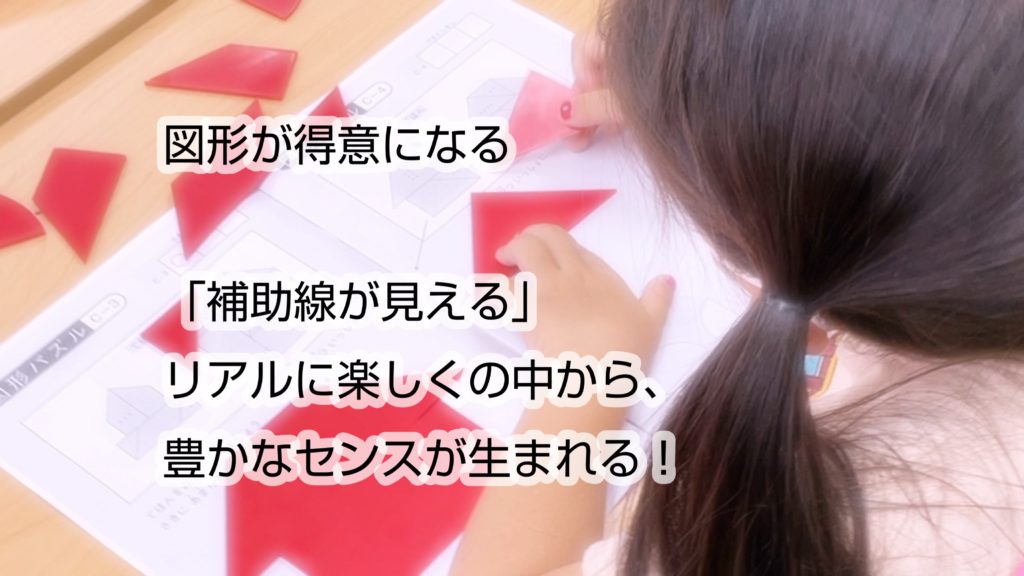
こんにちは、三重県名張市の個別指導塾 学びスタジオの奧川悦弘です。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今回は、図形について書きます。
複雑な図形の問題は、補助線を引くことができれば、解くことができるようになります。
それでは、どうしたら補助線のイメージを持つことができるようになれるのでしょうか?
∴図形を得意にするために大切なこと
図形を得意にするためには、
次の2つのことが大切です。
❶図形をイメージする力をつけること
図形を書いて、
その図形にいろいろ書き込まず、
頭の中で図を回転させたり、
補助線を引いて考えられることです。
図をじっと見て、
どうするべきか頭の中で考えられることです。
❷実物に触れること
そのためには、
実際に、いろいろな形や立体を手に取って、
頂点の数を確認したり、
並べたり、積んだりして
感覚を磨くことが大切です。
∴図形が得意な子どもと、苦手な子どもの違い
図形が得意な子どもは、
図形をありのまま、
全体図形をとらえています。
一方、
図形が苦手な子どもは、
部分的な寄せ集めで図形をとらえています。
公式や定理を覚えていくらテストで高得点をとっても、
頭の中でイメージして解く訓練をしていないのであれば、
公式や定理の範疇でしか、
問題が解けなくなり、
図形のイメージが広がっていきません。
∴立体図形をイメージできるとは
四角形の輪郭の1辺を軸にして回転させると円柱ができ、
円を垂直に押し出しても円柱ができます。
このように、
ある立体形状をみて、
平面の押し出しなのか
平面の回転なのか
平面をある軌道にそって作ったスイープなのか
大きさの違う平面をつないだロフトなのか
頭の中で、
補助線を描きイメージできることです。
∴図形のセンスを身につけるための3つのこと
図形のセンスを身につけるためには、
次の3つのことを練習します。
①図形の実物を触ること
②その作業を長期にわたってすること
③頭の中に思い浮かべる努力を意識的に繰り返すこと
∴数理パズルと数理積み木で身につける
日常生活で、
いろいろな図形に触れることができます。
その日常生活の中で、
自然に図形のセンスを身につける子どももいると思いますが、
これは、偶然に頼ることになります。
そこで、
学びスタジオでは、
数理パズルと数理つみきを使って、少しずつ階段を上がるように、図形のセンスを磨いています。
図形のセンスが磨かれると、頭の中で補助線がイメージできるようになってきます。
∴まとめ。補助線が見える!
数理パズルで、平面感覚と数量関係を
数理つみきで、立体感覚を
磨いていきます。
子どもたちは、テキストの図形を見ながら、
「ああでもない、こうでもない」と
頭と指先を使い試行錯誤しながら、
楽しく練習して、補助線の感覚を育てます。
リアルに楽しくの中から、豊かなセンスが生まれていきます。