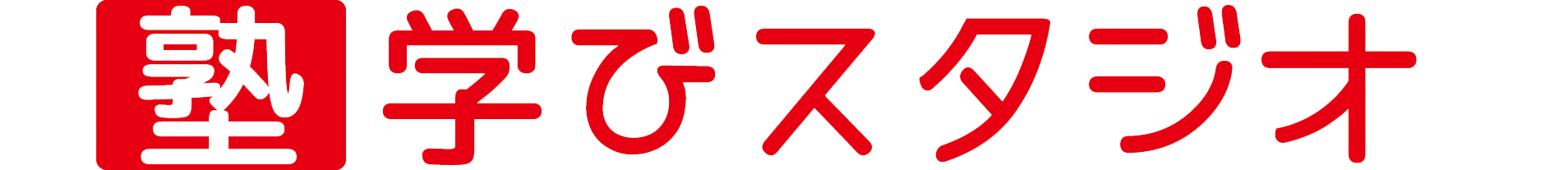学びスタジオ名張赤目教室
子どもの問題は、親の問題、親子の問題
子どもが遭遇する問題は、親の問題として、親が解決するのではなく、親子の問題として、一緒に考えましょう。
考えて決めたことを子どもの口から話してもらいます。あたかも子どもが自分で考えたように。
その積み重ねが、自分の問題を、自分で解決することにつながっていきます。
思考力・判断力・表現力の源になっていきます。
そして、子どもは自立に向かって進んでいきます。
「集中しなければ」というプレッシャーはいらない
集中には、外に狭く集中、内に狭く集中、外に広く集中、内に広く集中、4つの集中モードがあります。
暗記、理解、要点把握、問題解決など勉強内容に、この集中モードを合わせることにより、勉強の方向が明確になり、学びのパフォーマンスを高めることができます。
察しの悪く、面倒くさい親でいましょう
“察しが悪く”“面倒くさい”親になって、子どもの言葉を引き出しましょう。
また、親の発言は、省略せずに、5W1Hと助詞をつけた文章で話しかけましょう。
そうすれば、子どものことば力が育っていきます。
そして、ことば力は、友達との交流関係を拡げ、刺激を受けながら、その刺激がいろいろな物事や方向に興味をいだかせるようになります。
"いい先回り"は子どもを弱くしない
失敗させないように先回りすることは、子どもを弱くするかもしれません。
失敗から学ぶことをたくさんあるからです。
しかし、失敗はいい経験だからといって、失敗ばかりさせるのも、心が折れ、失敗を恐れるようになります。
子どもの行動をしっかり観察し、失敗と心のバランスをとって、さりげなく”いい先回り”をしてあげましょう。
読書好きになるレシピ
子どもは、ともとも読書を楽しむ能力を持っています。
絵本、児童童話の楽しい世界へ、親の優しい読み聞かせで誘ってあげれば、ある時、自発的に読み始めます。
そして、名作童話や小説のファンタジーの世界に夢中になっていくでしょう。
"鍛える"より"認める"ことがチャレンジ精神を育てる
子どもは失敗することが仕事です。
その失敗を責め、なじり、打たれ強くなるように"厳しく鍛える"ことは、悔しさや怒りから行動を掻き立てることになります。
そうではなく、子どものチャレンジ精神を認め、失敗しても責めずに肯定して、失敗から、一緒に学ぶことで、自ら高めること、強いメンタルを育てていきましょう。
読書は"繰り返し"から
読書は"繰り返し"から
子どもにとって、周りは知らないことの連続です。
その中で、繰り返し同じ物語を読んでもらいたがります。
知っている物語を聞いてホッとします。
この安心感が大切で、この安心感があるから、主人公と一緒にする冒険を思いっきり楽しむことができます。
そんな物語を心の書棚にたくさん持つことは、宝物をたくさん持つのと同じように貴重なことです。
成功は、"する"というより"気づく"もの
成功は、"する"というより"気づく"もの
物事を成功と失敗のものさしで見ると、失敗は否定的に捉え、何も得るものはありません。
しかし、失敗を肯定的に見ると、失敗は"気づき"に変わります。
そして、その"気づき"は成功につながっていきます。
それが、真の成功です。
小さな自信が、謙虚さを育て、大きな自信につながる
自信がないと、自分を卑下してしまったり、それを隠すために傲慢になったりします。
小さな自信の積み重ねが、物事をありのままに"謙虚に"受け止める感情を育て、やがて、大きな自信をつながっていきます。